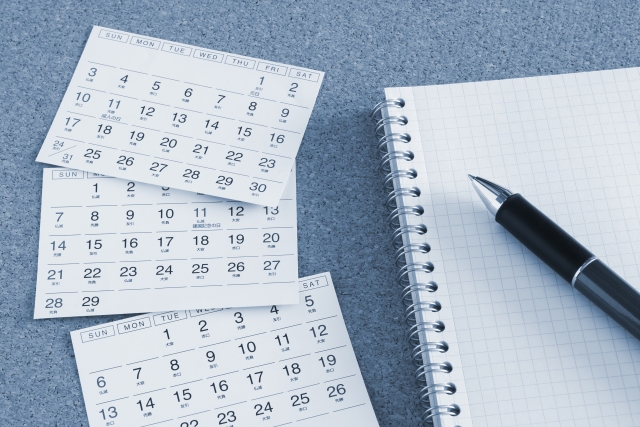
退職前後の生活について、何となく退職し、退職後はゆっくり休んでから考えようとしていました。
退職前後に、何をするかという具体的な行動予定がわからないことに、漠然とした不安を感じました。
退職することは決めたので、退職前後の行動予定を決めて、不安なく、退職前後を過ごせるようにします。
情報が古いと役に立たないので、最近発行された本の中から役立ちそうな、以下の2冊の本を購入し、読みました。
具体的には、よくわからなかったので、年金事務所、ハローワークと市役所に行ってきました。
全国健康保険協会の窓口は閉鎖されているので、行っていません。
退職前
国民健康保険、失業保険、厚生年金と国民年金については、準備はありません。
ハローワークに行く前に、履歴書、職務経歴書を記述して持っていくと就職活動がしやすいです。
退職と再就職を決めたなら、履歴書と職務経歴書を用意しましょう。
「履歴書」と「職務経歴書」のフォーマットをWordで作成し、アップロードしました。
右クリックしてダウンロードして、ご利用ください。
健康
国民年金と厚生年金を支払っている間に、病気を発見し、治療し、障害が残った場合に、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。
初診日が、国民年金と厚生年金を支払っている間という条件があるので、退職前に検査します。
検査した結果異常が見つかれば、国民年金と厚生年金を支払っている間に病院に行き、初診日を確定します。
人間ドック
毎年受診している人間ドックです。
オプション検査を全て追加すると、42万円ぐらいになります。
どのオプション検査を追加するのかについては、これから検討します。
- ドゥイブス検査
- 頚部超音波検査
- VSRAD検査
- 心臓超音波検査
- 胃内視鏡検査
- 前立腺MRI検査
- B型肝炎検査
- C型肝炎検査
- 梅毒感染症検査
- HIV検査
- 腫瘍マーカー検査(基本セット)
- 腫瘍マーカー検査(消化器セット)
- 抗p53抗体
- 血圧脈波検査
- 心不全マーカー血液検査
- RLP(レムナント様蛋白) コレステロール検査
- 軽度認知症検査(MCIスクリーニング検査)
- リウマチセット
- 甲状腺ホルモンセット
- 胃炎検査
- ロックスインデックス検査
- アミノインデックス検査
- 認知症検査
- 善玉脂質ホルモン血液検査
- サインポスト遺伝子検査
- 画像CD
- 報告書
歯科検診
虫歯があるわけではないですが、退職前に歯科検診を受診します。
眼科検診
視力は落ちていますし、退職前に眼科検診を受診します。
退職後
離職票を入手したら、離職票、年金手帳と運転免許所(身分証明書)を持って、月額400円の付加年金を支払うかどうかを決めて、すぐに年金事務所に行きます。
60歳の誕生月までの国民年金の納付書(国民年金保険料納付案内書)を受け取り、コンビニ等で支払います。
厚生年金に関することは何もしなくて良いです。
年金事務所に行った翌日8時30分に、離職票、運転免許所、マイナンバーカード、年金手帳と銀行口座のキャッシュカードを持って、市役所に行き、国民健康保険に加入し、限度額適用認定証を発行してもらいます。
少しでも遅れると、窓口が込み合い、待たされる可能性が高いです。
手続き自体は、15分程度で終わるそうです。
保険証は、2年ごとの更新になり、簡易書留で郵送されます。
市役所に行った翌日8時30分に、離職票、運転免許所、マイナンバーカード、銀行通帳かキャッシュカードにシャチハタではない印鑑と障碍者手帳を持って、ハローワークに行きます。
離職票は、提出すると返還されないので、事前にコピーを取っておきます。
少しでも遅れると、ハローワーク恐ろしいほど込み合っていて、立って長時間待たされる可能性が高いです。
税務署で、確定申告の方法を教えてもらいます。
60歳の誕生月に、年金手帳、運転免許所(身分証明書)、預金通帳と届出印を持って、年金事務所に行き、国民年金任意加入制度に加入します。
65歳の誕生月に、年金請求書が郵送されてきます。
年金請求書を持って、年金事務所に行って、専用銀行口座に振り込んでもらうように手続きをします。
65歳から「地域包括支援センター」が利用できるので、行ってみます。
まとめ
本を読むと、退職前後の生活が、把握することができます。
本を読んだだけでは、具体的に何をすれば良いのかわからずに、混乱し、不安になります。
実際に年金事務所、ハローワークと市役所に行ってみると、具体的に何をすれば良いのかがわかり、行動予定を整理でき、安心できるようになります。
退職前後に何をするのかは、大体同じなので、本は、多くの人に役立ちます。
50代になった人は、本を読んで退職前後の行動予定を作成することをお勧めします。
次回は、自己啓発の本である「希望をはこぶ人」という本について書く予定です。
ご期待ください。
以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。





